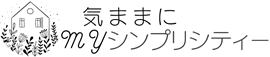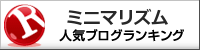今日は、『汚部屋は何によって形成されるのか?』について、考えてゆきたいとおもいます。シンプルライフを目指して家をきれいに改築したのに、なぜかお部屋の中が片付けられないという方がいました。
収納がたくさん!でもモノが溢れてる?
子供達が全員巣立ち、夫婦2人だけの生活がはじまったのを機に、大掛かりな家のリノベーションをした方がおられます。
それまでは、各自の部屋に別れていたけれど、壁を全部取っ払って「広々とした寝室」にしたり、一部屋丸ごとワーキングクローゼットにしてしまったり、キッチンをヨーロッパ製のものに全取り替えしたり、など理想通りの我が家に作り替えたそうです。
話しを聞いていると、きっとオシャレな設えで素敵なんだろうな〜と、こだわりのお家が目に浮かんでくる様です。
もちろん、大きなお家だから収納はたっぷりあります。クローゼットも大きいし、その中の棚も設えになっています。
ところが、クローゼットの中が空っぽ!?それはなぜ!?
広い家なのに、モノが外に積み重なってる
「そんなに大きな収納クローゼットもあるのに、なぜしまわないのですか?」と聞いてみると、こんな答えがかえってきた。
「今、ここで “選ぶ” という行為をせずに、全部クローゼットの中に押し込んじゃったら、おそらくこの先何年間も片付けなどしないんじゃないか!?という心配があるから。」
確かに、その想いは本質的だなと思います。そして、心配していらっしゃることも理にかなっていますね。
クローゼットにモノをしまう前に、必ずやらなくてはならないこと。それは『選別』の作業です。
『全部のモノを一カ所に集める』そして、それらを『一つ一つみてゆく』。そういった“選別”の作業を、クローゼットの中にしまう前に、行わなくてはならないですよね。
断捨離以前の問題です。断捨離する前に“選別”の作業をしなくてはなりません。
彼女は、ここのステップで躊躇してしまっているわけですね。
なぜ片付けの作業ができない!?
端から見ていたら、お子様達も巣立ったということだし、焦らずにゆっくりと片付けをしていってもいいのかも、とも思えます。
ただ、膨大なモノが外に出っぱなしというのも、気分わるいでしょうね。。。
片付けにあてる時間もある。収納スペースも十分にある。それなのに何もしない。
片付けないどころか、「汚部屋」ができてしまったり、リビングがモノで溢れたりしている。
これって、いったいどういうことなんでしょうか!?
え!?そんな意外な理由で片付けられないの?
実はこれ、『自己イメージ』の問題なんです。
自己イメージというのは、「私ってこんなヒト」という自分が思う自分についての観念です。
生まれてからこれまでの、様々な体験や見聞きしたことに基づいて構築されてゆくのが自己イメージです。
自己イメージができる要素は、
・自分で勝手に思い込んでいるもの、
・学校で「あなたって◎◎な人だよね」と定義付けされたもの、
・親に「あんたはいつも△△なんだから」と言われ続けたもの、
・幼少の頃からの環境、
・人にけなされたもしくは尊敬されたなどの体験、
・インパクトのある経験から学んだこと、
などが例としてあげられます。もちろんそれだけではありませんけどね。
どんな暮らしをしている自分が、自分らしい?
この問いは、自己イメージに照らし合わせることで、無意識レベルで自己チェックが行われます。
例えば、「汚く臭い部屋で混沌としている自分」という『自己イメージ』を持っていたとします。
その人が、ホテルのようにきちんと片付いてて清潔な部屋に引っ越しをすると、非常に居心地が悪く感じてしまうでしょう。
自己イメージと合致していない状態ならば、ちゃんと自己イメージにマッチした状態に『変化』させてゆく必要があります。これは、意識ではなく無意識レベルで行われます。
この例のケースでは、ホテルの様な部屋を徐々にガラクタでいっぱいにし、掃除を怠り、汚部屋にしてゆく。
そうすることで、自分の持つ自己イメージに合致した環境で暮らすことができるようになるというわけです。
これとは逆に、
「いつも清潔で片付いた部屋でミニマルな生活をしている自分」という『自己イメージ』を持ってる人がいたとします。
その人が、何かの拍子に、汚くて臭い汚部屋に入居することになったとすると、非常に居心地が悪く感じますよね。
でも、自己イメージと合致していませんので、大々的に片付けしたり、飾り付けをしたり、徐々に自分の自己イメージに合った部屋に改造してゆくことでしょう。
自己イメージに合った『状態』を、無意識が維持してゆこうとする力。
これが、「片付けたいのに片付けられない」の一番の理由です。
人の脳のはたらきをみてみると
「自己イメージ」と「片付けられない」が、なぜ結びつくのか?について、お話ししますね。
すごーく大雑把に言うと、人の脳はこの3つで成り立っています。
・爬虫類脳
・ほ乳類脳
・人間脳
下に進むにつれて、より高度な思考ができる脳になります。
そして、実際にはもっとも原始的な『爬虫類脳』が、意識の大半を占めるようになっています。
爬虫類脳は、原始的な欲求を満たしたいと思ったり、恐怖を回避しようとする行動をとらせたりします。
「死にたくない」とか「食べたい」とか「眠りたい」などの基本的欲求を満たそうとする脳です。
例えば、山道を歩いていて息が切れてきたら、呼吸を整えようとして自動的にハーハーします。誰も「あ、いま山道を登ってるんだから、ハーハーしなくっちゃ!」と思ってから意図的に、ハーハーしないですよね。自動的になるのは、「死なないように」管理してくれてる『爬虫類脳』のおかげです。
片付けられないのは、何のせい?
基本的に、
『手っ取り早く、楽に、欲求を満たしたい』のが、爬虫類脳ですね。
こういった本能的なメッセージを発している『爬虫類脳』に対して、『人間脳』が、考えを制します。
『甘いものもっと食べたい(爬虫類脳)』と思うと=> 『いやいや糖尿病に悪いからやめとこう(人間脳)』と制してくる、という感じです。
爬虫類脳からの指令で片付けられない
さてさて、話しを元に戻します。
『自己イメージを維持』する働きは、どの脳が司っていますか!?
そうです!爬虫類脳です!
「今まで生きてたんだから、これまでと同じように生きていたら、死なないよ」という、爬虫類脳の根本的恐怖に基づいたものです。
ようするに、「変わっちゃダメ!」「変わったら死んじゃうかもよ!」という指令が爬虫類脳から出されてしまうんです。
自己イメージを維持しようとするのが爬虫類脳のおしごとなのですから。
ようするに、『変わらないこと』を指令として出しているということです。
「モノを選び抜くこと」それは、「人生を選び抜くこと」と同じですよね。大きく人生が変わってしまうのが、お片付けです!
だからこそ、恐怖なんです。爬虫類脳の判断で、生死にまつわることとして制御されてしまうんですね。
あなたの自己イメージは?
自分の持つ自己イメージは、ことあるごとにアップデートしてゆくべきです。
もし何もせずにそのままだとしたら、自己イメージが変わる速度が遅くなるか、一生変わらない自己イメージを持ち続けることになるか、ではないでしょうか。
もしも誰かが、『自分の大好きなモノだけに囲まれ幸せな生活をしてる』という自己イメージを持っていたとしたら、その人にとって「片付け」は容易にできることではないか、と思います。
でも、別の人が 『欲しいものが手に入ったなら、別の何かをあきらめるべき』という自己イメージを持っていたとしたら、「家を好きなように改装したなら、不快な状態も同時に受け入れるべし」
(>o<)、などというメッセージが爬虫類脳から届いてしまうでしょう。
これ、意外と多いんですよね。
昭和な親御さんたちの教育方針でしたから。教育方針のトレンドっていつの時代でもありますよね。
昭和の子供達は、「おとなしくしてたら飴をあげるね」とか、「宿題やったらテレビ見ていいよ」とか、トレーディング教育で育ってきていますから、すっかり交換条件が見に染み付いてしまってる人おおいです。
あなたはどうですか!?
この思考が邪魔するおかげで、片付けが滞ったりしますか?
じゃぁ、どうしたらいいの?
無意識レベルで深く刻み込まれた自分史ともいえる『自己イメージ』。どうやって変えたらいいの?
どうやったらキレイな部屋に住んでるという自己イメージを変えて、片付けがすんなりできるようになるの?
とっても長い投稿になってしまったので、次回に譲ります。
『解決編』として、次の投稿に載せますね!
ご訪問ありがとうございました!

ブログ村ランキングへの応援クリックいつもありがとうございます!ブログ更新の励みになっています♪